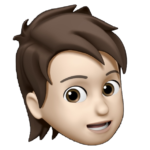『この夏の星を見る』原作の感想と見どころ|映画化前に知りたい登場人物と魅力

2025年7月4日、辻村深月さん原作の青春小説『この夏の星を見る』が映画化され、ついにスクリーンに登場します。
2020年、コロナ禍という未曾有の時代を背景に、離れた場所に暮らす若者たちが“星”を通じてつながっていくこの物語は、静かで、優しく、力強い共感を呼び起こします。
この記事では、「この夏の星を見る」作品の魅力を深く掘り下げていきます。
原作を読んだ読者の感想、映画化への期待、登場人物の背景やテーマ、ロケ地の雰囲気などを交えながら、感動の本質を丁寧にご紹介します。
失われた時間を星でつなぐ──3人の主人公たち
『この夏の星を見る』の原作では、心に残る3人の若者が登場します。
高校2年生の亜紗は茨城の天文部員。
合宿の中止や行事の制限により、楽しみにしていた青春が削がれていく現実に苦しみます。
東京では、真宙という中学1年生の少年が、クラスに男子が自分一人だけという孤立感と闘っています。
そんな彼が、「リモートで星を観測する」という新しい出会いの中で、世界とのつながりを見出していきます。
そして、長崎・五島列島の高校3年生・円華。彼女は観光業を営む家の事情とコロナ禍による偏見の狭間で揺れています。
ある誘いから足を運んだ天文台で、彼女の心が静かに変わり始めるのです。
「この夏の星を見る」原作を通じて感じるのは、それぞれの土地、それぞれの痛みに寄り添う優しさです。
若者たちの内面が丁寧に描かれることで、読む人の心にそっと寄り添い、忘れがたい余韻を残します。
原作を読み始めた時、「この夏の星を見る」としてまず感じたのは、それぞれの主人公たちの抱える孤独のリアルさでした。
コロナ禍での心情の描写が丁寧で、「自分もあのとき、こんな気持ちだった」と自然に感情移入できたのです。
スターキャッチコンテスト──孤独の中の希望
天文部のイベント「スターキャッチコンテスト」は、『この夏の星を見る』原作における象徴的な存在です。
望遠鏡をのぞいて星をいち早く捉える競技──それ自体は小さな活動かもしれませんが、離れていてもつながるという希望の象徴として描かれます。
「この夏の星を見る」に触れた人が必ず感じるのは、この静かな挑戦が、どれほど大きな意味を持つかということ。
誰とも会えない日々に、それでも誰かと同じ空を見上げることができた。
この静かな挑戦が、どれほど大きな意味を持つか。読者はその感動を胸に刻むことでしょう。
「この夏の星を見る」で印象深いのは、このコンテストに向かう過程での登場人物たちの葛藤と希望の芽生えでした。
読んでいて、胸がじんと熱くなる感覚があり、「諦めない姿勢」そのものに励まされたのをよく覚えています。
映画化によって広がる“静かな叫び”
実写映画として描かれる『この夏の星を見る』は、原作の感想を深めるうえでの大きな要素となります。
主演を務めるのは桜田ひよりさん。
亜紗の繊細な感情を、視線や沈黙、わずかな呼吸の揺れで丁寧に演じることが期待されています。
監督は若手の山元環さん。
コロナ禍でのマスクで顔が隠れるという制約すらも、映像表現に活かすという独自の挑戦は、まさに“今を生きる私たち”のリアルを描く試みです。
『この夏の星を見る』を読んだうえで映画を観れば、視覚と音が加わることで一層深く物語に没入できるはず。
音楽を担当するharuka nakamuraさんの静謐な音色も、物語の世界観と完璧に調和しています。
「この夏の星を見る」として映画を観た後に読み返すと、映像と文章が互いに補完し合い、より深い理解と感動が得られる構造になっていると感じます。
登場人物の関係図──交差し、支え合い、広がる心の輪
原作『この夏の星を見る』では、主人公たちは直接的に深く関わるわけではありません。
それでも、彼らの視線の先にある“星”が、彼らをそっと結びつけていきます。
会話がなくても、同じ空を見上げる記憶がある──その感覚こそが物語の核です。
控えめでありながらも確かなつながりを描く手法に、静かな感動を覚えることでしょう。
原作の中盤、「この夏の星を見る」として特に印象的だったのは、画面越しに心が重なっていくようなあの瞬間。
孤独のなかにぬくもりを感じる描写がとても印象に残りました。
ロケ地予想と映像への期待──「ありふれた景色」の特別さ
本作は、茨城・東京・長崎と日本各地を舞台に展開されます。
映画では実際の高校がロケ地として使用されており、『この夏の星を見る』原作の空気感を忠実に再現しています。
特別ではない、どこにでもあるような風景。だからこそ、そこに映し出される「誰かの想い」が、観る者の心に沁みわたるのです。
『この夏の星を見る』が描いた“静けさのなかの熱量”を、映像でもきっと感じられることでしょう。
特に終盤に近づくにつれて、原作で描かれる景色が心象風景と重なり、ページをめくるたびに胸があたたかくなる感覚がありました。
辻村深月という作家──“見えない心”をすくい上げる人
『この夏の星を見る』を語るとき、やはり辻村深月さんという作家の存在に触れずにはいられません。
彼女の作品には一貫して、“言葉にならない感情”をすくい上げる視点があります。
派手な展開や衝撃的なラストではなく、むしろ日常のなかに埋もれてしまいそうな小さな「心の揺れ」を、丹念にすくい上げて物語に変えていく。
『ツナグ』『かがみの孤城』『名前探しの放課後』──どれも、一見すると普通の青春小説やミステリーの形をしていますが、読後に残るのは“癒し”や“肯定感”のような温かな感情です。
そして『この夏の星を見る』もまた、そんな辻村作品らしい“そっと寄り添う物語”のひとつだと感じています。
彼女が描く「星」は、ただの象徴ではありません。
心のなかにある“確かに存在するけれど、誰にも見せられない痛みや希望”を、私たちに見えるかたちで照らしてくれるものなのです。
だからこそ、辻村深月という作家をまだ知らない人にも、この作品をきっかけに知ってもらえたら──。それはきっと、とても素敵な出会いになるはずです。
「この夏の星を見る」の原作を読了した直後に私の中に残ったのは、登場人物たちだけでなく、読者自身に向けられた優しい眼差しでした。
自分の小さな感情を肯定してくれるような温かさに、深く救われたのです。

まとめ──“この夏”を、きっと忘れない
誰かと一緒にいること。自分と向き合うこと。言葉にならない感情を、ただ“見上げる”ことでつなげる物語──それが『この夏の星を見る』です。
「この夏の星を見る」として、今を生きる私たちが、この物語から受け取れるものは決して少なくありません。
あの時の不安も希望も、見上げた空にあったこと。誰かがいて、自分がそこにいたこと──すべてをそっと肯定してくれる作品です。
映画を観る前に、あるいは観た後に、もう一度ページをめくってみてください。『この夏の星を見る』の世界は、きっとあなたの記憶の中にやさしく灯り続けるでしょう。